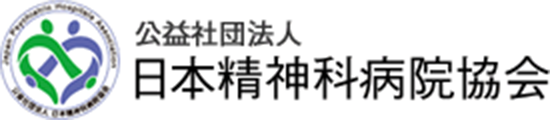NEWS お知らせ
9月21日は、「認知症の日」 ~ 世界アルツハイマーデー ~

2023年6月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立、施行されました。
2024年から毎年9月が「認知症月間」、9月21日が「認知症の日」と定められました。また、国際アルツハイマー病協会(ADI)は1994年の国際会議で世界保健機関(WHO)の後援を得て、9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し認知症の啓発を実施しています。
認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することが明記されています。この中で「新しい認知症観」が示されました。
「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。認知症の人が認知症の状況に応じて、最後まで自分らしく暮らせるよう、周囲の人の支えも得ながら認知症の人の尊厳を保持できるようにすることが重要です。
2024年12月に「認知症施策推進基本計画」が示され、これに基づき、地方自治体は計画を策定しています。具体的な施策として、「認知症ケアパス」のさらなる周知、認知症カフェへの参加、ピアサポーターによる本人支援の推進、認知症サポーターの養成と支援者をつなぐ仕組み(チームオレンジ)、さらに認知症の人の社会参加活動の体制整備が行われています。地域包括ケアシステムの実現に向けた高齢者の社会参加や介護予防に向けた取り組み、配食・見守り等の生活支援体制の整備の推進も進められています。
認知症の医療においてはアルツハイマー病の軽度認知障害(MCI)の抗体薬治療が認可されましたが6~7ヶ月発症を遅らせるというもので、使用に当たっては対象基準が厳しく、副作用の頻度も高いことからあまり普及されていません。最も大切なことは、超軽度・軽度の段階で診断を受けた場合、その後何十年と病気と向き合うことになります。診断後支援を本人・家族等と長期間に渡り行っていけるのは精神医療であります。多職種連携によるチーム医療、介護サービス等と共同して人生を支えることが重要であります。
(常務理事 渕野勝弘)