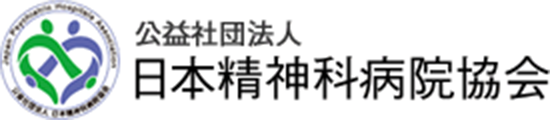NEWS お知らせ
山崎会長就任挨拶 -九期目会長に就任して
 6月13日、パレスホテルにて開催された第27回定時社員総会において、就任以来9期目の会長に推挙されました。
6月13日、パレスホテルにて開催された第27回定時社員総会において、就任以来9期目の会長に推挙されました。
国際的な混乱の中で急激なエネルギー価格の上昇、物価高騰に揉まれて我が国の医療を中心とした経済環境は3/4の病院が赤字経営を余儀なくされるといった未曽有の混乱に巻き込まれています。民間精神科病院においても同様な赤字経営を余儀なくされています。
令和6年6月に行われた診療報酬改定も財務省主導で社会保障費削減目標に沿った実質マイナス改定に終わりました。その後の諸物価の高騰によって病院の赤字幅は大幅に膨れ上がり、地域の精神科医療体制を脅かす状態になっています。
一般企業では6%を超えるベースアップが常識になっている時代に、医療職については2.5%と約半分のベースアップ財源補填に終わった結果として、医療職から一般企業に多くの人材が流出し、医療における人材不足に拍車がかかっています。一方で1億2千万人をピークに人口減少時代に入り、人口減少に比例して社会的インフラのダウンサイジングも考える時代に入っています。
精神科病床についても既存病床約32万床、基準病床約26万6千床、実質稼働病床約26万床と基準病床を約6千床下回るところまで病床稼働率が低下しています。こうした現象は新型コロナ感染症をきっかけに起こったと思われがちですが、少子化による新患の減少、向精神薬の開発による入院の短期化、統合失調症の長期入院患者の高齢化、株式会社経営の介護・障害者施設の激増といった長期入院患者の取り合いの結果と考えられます。
いままで単科精神科病院として精神科地域医療を支えてきた会員病院の多くは、これまで述べた社会的要因によってそれぞれの地域特性を踏まえた医療・介護・障害を組みこんだステーションに脱皮していく必要性に迫られています。休床病棟の買い上げ、施設転換、病床のダウンサイジングを含めた多機能化による経営の健全化を模索する時期に来ていると実感しています。このための財政的支援を国に求めていかなくてはなりません。
また精神科医療も参画することになる地域医療構想において、地域医療・介護・障害資源を使った地域精神科医療体制をどのように構築していくのかも大きな課題です。この中で日精協会員病院が行ってきた精神科一次救急体制を精神科診療所中心としてどのように構築していくかも大きな課題になってきます。そして「かかりつけ医」の議論で抜けていた準夜診療の義務化を同時に検討する必要があると考えています。このことは一般科のようには今まで議論されなかった精神科診療所と精神科病院の守備範囲を決めるロードマップを示して診療報酬改定の中でメリハリのついた政策誘導を行っていこうと考えています。